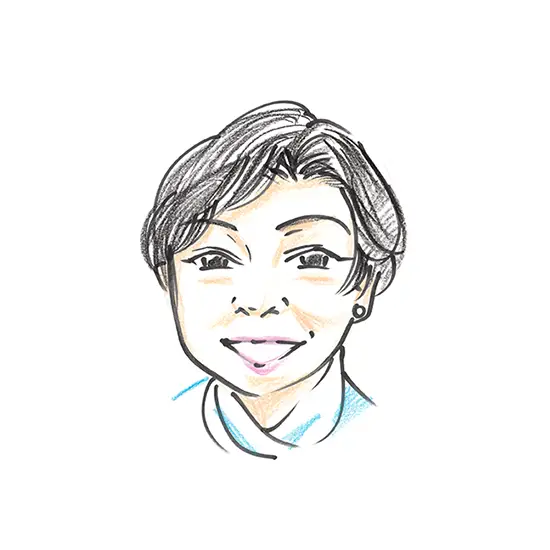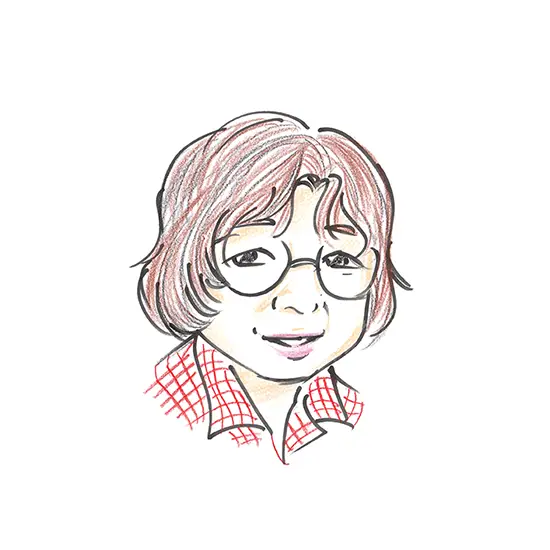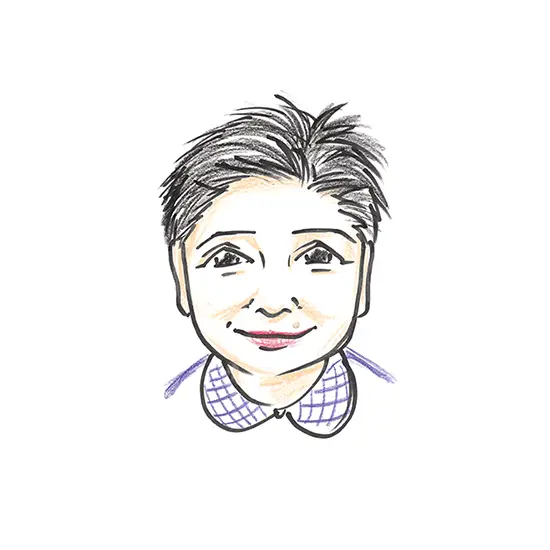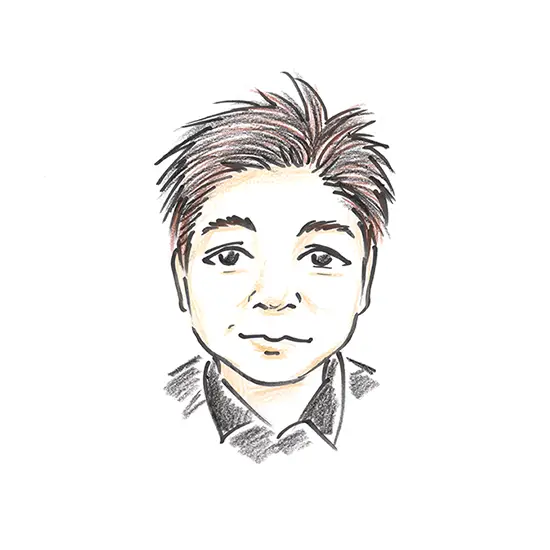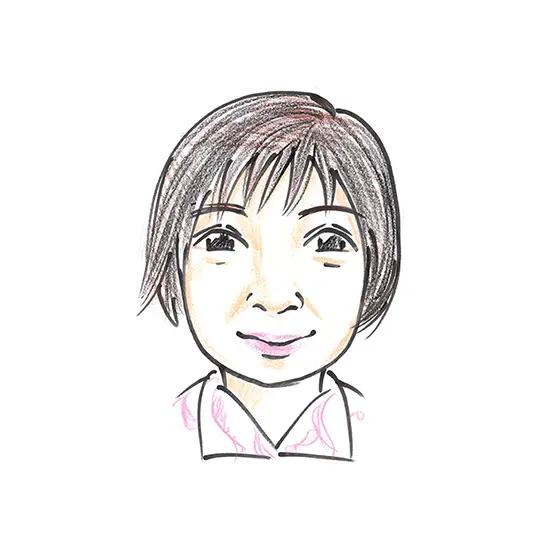
代表理事
堅田 雅子
障がいのある子どもを授かったことをきっかけに、同じ状況の母親たちが集まり、親の会を立ち上げました。障がいのある子どもたちを取り巻く環境を理解することで、ニーズと制度の間に隔たりがあることを実感し、自分たちで解決策を模索し始めました。当時、障がいのある子どもたちが安心して過ごせる場は学校と家しかなく、母子共に引きこもってしまうことが多くあったことから、学校の休み期間中に過ごせる心地よい居場所を作ること、障がいの種別や障がいの有無を問わないインクルーシブな環境を作ることなど、具体的な取り組みをおこないました。
障害のある子どもとその保護者を中心に、関係者全体(医療、教育、福祉、地域など)が一堂に会し、子どもたちの問題を共有・検討する会を開催。その後、相談専門員の配置と担当者会議の開催を実現。さらに、医療的ケアが必要な子どもが保護者なしで学校に通う(単独登校)ために取り組む会を立ち上げ、山口県で単独登校を実現させました。
NPO法人化した親の会はさらに社会的な立場を持ち、山口市の施策に関する委員や国の科研費調査協力委員、県民活動のアドバイザーなどを務めるようになりました。身近な人と悩み相談ができる保護者同士のピアカン、意思伝達がうまくいかない方々に有意義であるDX化を見据えたプログラム、ストレス緩和のためのスヌーズレン、有事の際にもサポートできるためのサポートブックのデジタル化など、障がいのあるみなさんが社会の一員として、また、一人ひとりが自分らしく輝ける未来を目指して数々のことを考え行動し、実現させてきました。そして、令和5年には、ここにある一般社団法人ゆうわを立ち上げ、ノーマライゼーションからソーシャルインクルージョンへと向かう一歩を踏み出しました。